外断熱専門のHLPは町田、相模原、武相地区を中心に外断熱住宅全てを二重断熱以上でお手軽価格で施工
| |
ミラウッディは(株)JSPという会社の製品で
熱や水をほとんど通さず室内の湿気は通す透湿性を持つのが特徴で、
厚さ6mm、幅1m、長さ15mのアコーデイオン状の板のような
形をしており本体を拡げて外断熱に関連して屋根の断熱材等に使います。
本製品は気密・防水性能をアップさせる為、シート同士の接続部分にアイジャクリ加工が施されています。
性能も良く、熱の移動割合は伝導10%、対流15%、輻射75%で
構成されますが今まで業界であまり注目されていないこの約7割を占める
『輻射』を効果的にカットできるので、外断熱に関連してミラウッディで施工すると
断熱性能が高いとされるウレタン系断熱材60mm相当にも
匹敵する性能を発揮します。
反射断熱工法は外断熱の一環としてこのミラウッディを用いて、熱の移動割合の大部分である輻射を抑制したり、熱を内部に伝えにくくして建物に負担の少なくする工法として普及が期待されています。
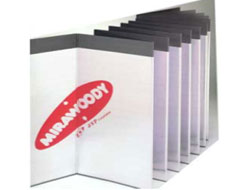
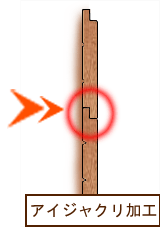
|
|
| |
宇宙空間からは地球に向けて『熱線』が、出ています。
熱線とは赤外線や電磁波の事で、この熱線そのものが熱を持っているわけでは
なく熱そのものは空気中のダストや水分粒子に衝突した時に
その内部分子を振動させることで発生します。
アルミ箔はこの熱の伝わるの要素のうちの
『輻射』の96〜97%を反射・遮熱する特性があり
この特性を当初NASAは衛星や宇宙服の熱制御材として利用していました。
ミラウッディはこの特性を応用し建築用遮熱材として改良した製品です。
ポリエチレンフォームを高純度なアルミ箔で挟み込む事で
輻射熱の96〜97%を反射・遮熱するので
6mm厚のシートが6cm厚のウレタンフォーム以上の効果を発揮します。
アメリカペンシルバニア大学のデータによれば
熱の伝わる要素は
伝導10% 対流15% 輻射75%で構成されているそうですが
日本では伝導と対流を遮る技術ばかりが追求され
成分の大部分を占める75%の部分はよく知られておらず
残りの25%にしか対策がされていないのが現状です。
|
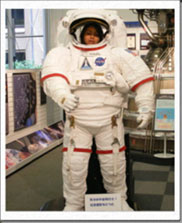 |
|
| |
|
|
|
|
| |
柱の外側に構造合板を取り付け、ミラウッディを貼り
杉の胴縁※1を取り付け、サイディングを貼り
※ラス板※2の上にも取り付け可能です。
胴縁がつくるすき間は空気の流れる通気層とし
柱の間には断熱材のウッドファイバー※3を充填します。
この方法で外壁を構成すると室内の湿気はウッドファイバーとミラウッディを通過し 通気層に出て外部に排出されます。
外からの熱は、ミラウッディにより遮断されるので
壁体内には入ってこず、そのことで結露が発生しにくくなり室内で発生する湿気は壁体内、通気層を通過し外に排出される効果が期待されます。
湿気を吸放出する断熱材ウッドファイバーとミラウッディの組み合わせにより、外壁通気工法と外断熱工法のよい点を取り入れた
「外断熱通気工法」が可能なのではと考えています。
ミラウッディは内側の湿気を外側に透湿する機能があるので
外断熱の一環として外壁に透湿機能のある素材を組み合わせ、断熱性能を保持しながら
湿気を逃がす効果が期待できます
※1
胴縁 「どうぶち」
胴縁とは、 壁の板張りやボード張りなどを受けるための下地部材
※2
ラス板「らすいた」

モルタル塗りの左官下地になるための板材。
この上にルーフィングなど防水紙を貼りラスを張ってモルタルを塗る
|
|
  |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
■屋根
建物を長持ちさせる為に徐々に熱を下げる為の「多重断熱構造」の屋根は
瓦素材の下に通気層→反射断熱層→外断熱層を設け
野地板下に通気層→ウッドファイバーを充填した小屋裏で構成される外断熱法の一種です。 |
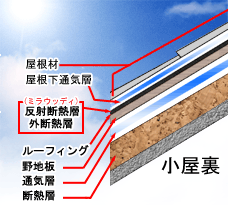 |
| |
■外壁
外壁は外壁素材→通気層→反射断熱素材→外断熱材→耐力壁材→通気層→
ウッドファイバー、そして壁内側に通気層を設けてます。
このような多層構造にして外部から建物内部への熱伝導をおだやかに
減衰させてゆく方法が
一番建物を長持ちさせる外断熱法と考えております。 |
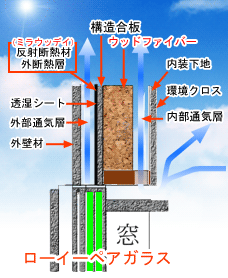 |
| |
一般的な断熱材は、熱伝導のうち1割を占める伝導熱を防ぎますが
この断熱材、正しくは文字通り熱を断つものではなく、
実際は熱を吸収してその熱を反対側に伝えづらくする材料です。
木造住宅で使われる材料のほとんどは反射率が低く屋内外の熱を吸収しますが
その中でも一番熱を吸収する材料は断熱材で、 この断熱材の性能が低いと外が涼しくなっても
家の中は熱気がこもったままになってしまいます。
この状態の家をエアコンで冷やしても冷気のほとんどは壁や天井などを冷やすのに費やされ
屋内自体がなかなか冷えず
冬は断熱材や建材が暖気を吸収して室温と平均輻射温度※1を下げてしまい
快適さが損われることがあります。
※1
平均輻射温度=室内であれば、床・壁・天井・サッシ・家具 それぞれの表面の平均温度。
一般的に、私達の体感温度は湿度や風などの条件を除けば、体感温度=(室温+平均輻射温度)÷2で表現されます。
ほとんどの場合、断熱材の選択基準として熱伝導率だけに目がいきがちですが
その性能がずっと続く訳ではなくカタログなどで公表されている数値は、すべて製造出荷時のものです。
もうひとつ重要なのは、吸水量です。 断熱材は、水分を含むと劣化します。
住宅は、50年、100年もつような構造にしたのに、断熱材は10年しかもたないでは意味がありません。
この吸水量を見ると素材の断熱劣化の早さがわかります。
ボード系断熱材は、吸水量の数値が大きいほど水や水蒸気を含みやすくなります。
・フェノールフォーム ・ウレタンフォーム 押出発砲ポリスチレン をクリックすると、その事がわかります。
■繊維系断熱材
これは私達が冬に着るセーターと同じ理屈の製品で
細かい繊維を絡ませて空気の取り込み熱の移動を防ぎますが
建物に置き換えてみると建物は1年中セーターを着せられている状態と同じです。
断熱材は、構造材の間に詰めるので断熱できない部分『熱橋』が出来てしまいます。
特に冬は冷やされた部分に暖かい湿気を持つ空気がぶつかり壁内結露や表面結露が生じ
建物の寿命や私達の健康に影響を及ぼします。
特に壁の伝熱は温度差があるほど激しくなりますが、これは間の空気層が熱伝導により暖められてしまい温度差が確保できなくなるためです。
ただたとえば屋根面裏や外壁と躯体※2の間に通気層を設ける時に
そこに反射断熱を使用すると間の空気は熱伝達されず
夏場は加熱された屋根から熱を通気層で逃がし遮熱するので
非常に効果があるという計算結果になりました。
※2
躯体 『くたい』
建物の、建具・造作・仕上げ・設備などを除いた部分。
建物の構造体の主な強度を受け持つ。
通常、躯体工事というと杭工事・土工事も含めて使われるが、 骨組みの工事だけをいう場合もある。
|
|
詳しくはお問い合わせ下さい
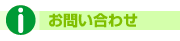

|